貯金だけではお金はなかなか増えず、物価が上がるとお金の価値が下がってしまう…。
将来に向けて資産は増やしたいけど「投資は難しそう」「リスクがありそう」と感じてしまう。
このように投資に興味はあっても、不安でなかなか始められない人も多いのではないでしょうか。
そんな中、2024年から新NISAがスタートしました。
新NISAは投資で得た利益が非課税になり、長期的に資産を増やしやすい仕組みが整っています。
とはいえ、デメリットやリスクが気になるのも当然です。
そこで本記事では、新NISAの仕組みやメリット・デメリットから始め方まで初心者向けにわかりやすく解説します。
この記事を読めば、新NISAの基本をしっかり理解して安心して投資をスタートできるようになるので、最後までご覧ください。
新NISAとは
新NISAは、投資で得た利益に税金がかからないお得な制度です。
本章では、新NISAの基礎知識に関する3つの項目について解説します。
・新NISAの制度概要
・NISAと投資信託の違い
・旧NISAからの変更点
この項目を理解すれば、新NISAについての理解を深められます。
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
新NISAの制度概要
新NISAとは投資で得た利益が非課税になる仕組みで、旧NISAと比べて柔軟な資産形成が可能になりました。
年間最大360万円まで投資でき、非課税で保有できる総額は1,800万円に拡大されたため長期的な資産形成に適しています。
新NISAの特徴は、投資の目的やスタイルに応じて使い分けられる「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類です。
以下の比較表で、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の特徴を確認してみましょう。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 投資対象 | 金融庁が指定した投資信託 | 上場株式・ETF・投資信託 |
| 年間投資上限額 | 最大120万円 | 最大240万円 |
| 運用スタイル | 長期・積立・分散投資 | 自由な運用(短期・中期・長期) |
| リスク | 比較的低い(リスクを抑えた運用) | 比較的高い(値動きが大きい商品も含む) |
| 売買の自由度 | 低い(積立のみ・頻繁な売買不可) | 高い(売買自由) |
| 投資の目的 | 安定した資産形成、長期的な資産の成長 | 積極的な資産運用、大きなリターンを狙う |
このように「つみたて投資枠」と「成長投資枠」にはそれぞれの特徴やメリットがあります。
自分の投資目的やリスク許容度に合わせて、どちらを活用するかを検討してみてください。
- つみたて投資枠:毎月一定額を積み立てて、安定的に資産を増やしたい人
- 成長投資枠:個別株やETFに投資して、値上がり益で大きなリターンを狙う人
それぞれの投資枠におすすめの人は上記のとおりです。
さらに新NISAではこの2つを組み合わせて、リスクを分散しながら自分に合った投資スタイルを選べます。
新NISAは年間360万円の投資枠と1,800万円の非課税保有限度額を活用し、初心者から経験者まで幅広く対応できる制度です。
NISAと投資信託の違い
NISAと投資信託は混同されやすいですが目的が異なります。
NISAは「投資をするための制度」であり、投資信託は「購入できる金融商品」の一つです。
NISAを利用すれば、投資信託だけでなく株式やETFなどにも投資できます。
以下の比較表で、それぞれの違いを確認してみましょう。
| 項目 | NISA | 投資信託 |
|---|---|---|
| 目的 | 投資の利益を非課税にする制度 | 投資家から集めた資金を運用する金融商品 |
| 対象 | 株式や投資信託などの金融商品 | 複数の株式や債券など |
| 運用の仕組み | 投資家が自分で商品を選んで購入 | 運用のプロ(ファンドマネージャー)が運用 |
| 投資の特徴 | 税制優遇を活かして資産を増やす | 分散投資でリスクを抑えつつ運用可能 |
| リスク | 投資商品によって変動(値下がりの可能性あり) | 比較的低め(分散投資によるリスク分散) |
| 購入できる商品 | 投資信託・株式・ETFなど | 特定の株式や債券などの組み合わせ |
NISAは投資の利益が非課税になる制度であり、投資信託は運用のプロが複数の資産に分散投資する仕組みを持つ金融商品です。
そのため、NISAを使えば投資信託をはじめとするさまざまな金融商品に投資しながら、税制メリットを活かした運用ができます。
- NISA:投資で得た利益を非課税にし、株式や投資信託などに投資できる制度
- 投資信託:運用のプロが複数の資産に分散投資し、リスクを抑えながら資産を増やす金融商品
それぞれの特徴を理解し、自分の投資目的に合った方法を選ぶのが大切です。
旧NISAからの変更点
新NISAは旧NISAと比べて大きく制度が変わり、より長期的な資産形成がしやすくなりました。
以下の比較表で、新NISAがどのように変わったのか確認してみましょう。
| 項目 | 旧NISA | 新NISA |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 一般NISA:5年 つみたてNISA:20年 | 無期限 |
| 年間投資枠 | 一般NISA:120万円 つみたてNISA:40万円 | つみたて投資枠:120万円 成長投資枠:240万円合計360万円 |
| 非課税保有限度額 | 一般NISA:600万円 つみたてNISA:800万円 | 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円まで) |
| 投資可能な商品 | 一般NISA:株式、投資信託など つみたてNISA:一定の投資信託のみ | 株式、ETF、投資信託など |
| つみたて投資枠と成長投資枠の併用 | 不可 | 可能 |
| 売却後の枠の再利用 | 不可 | 可能 |
| 口座開設可能期間 | 一般NISA:2023年まで つみたてNISA:2042年まで | 恒久化(期限なし) |
新NISAでは投資の自由度が増し、長期的な資産形成を目的とした運用がしやすくなりました。
特に売却後も枠を再活用できるため、資金を効率的に動かしながら投資計画を立てられます。
新NISAでは売却枠が復活するので、「途中で資金が必要になったから売却したけれど、また投資を再開したい」という場合にも柔軟に対応できます。
旧NISAでは「一般NISA」か「つみたてNISA」のどちらかしか選べませんでした。
しかし、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用できるため、積立投資と個別株投資を組み合わせた柔軟な運用が可能です。
新NISAは投資の幅を広げながら、計画的に資産を増やしやすい制度へと進化しています。
新NISAのメリット
新NISAには投資可能額の拡大や非課税期間の無期限化など、多くのメリットがあります。
年間最大360万円の投資ができ、非課税で運用できる総額も1,800万円に拡大されたため長期的な資産形成がしやすくなりました。
本章では、新NISAの具体的なメリットについて解説します。
・投資可能額・非課税保有限度額の拡大
・売却して空いた枠を再度利用できる
・非課税保有期間が無期限になる
・「つみたて投資枠」は手間がかからず、投資タイミングの判断が不要
・「成長投資枠」では個別株やREITなど自由度の高い投資ができる
・100円など、少額でも投資を開始できる
これらのメリットにより、新NISAは初心者でも無理なくスタートできるだけでなく、経験者にとっても資産運用の自由度が高い制度となっています。
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
投資可能額・非課税保有限度額の拡大
新NISAでは投資可能額が大幅に増え、より効率的に資産形成ができるようになりました。
年間投資枠は最大360万円、生涯非課税投資枠は1,800万円と、旧NISAと比べて大幅に拡大されています。
しかし、新NISAではより多くの資金を非課税で運用できるため、資産形成のスピードが向上します。
年間300万円ずつ投資すると、わずか6年で非課税枠の1,800万円を使い切ることが可能です。
新NISAでは投資可能額の拡大により、資金を多く投入するほど運用益を非課税で受け取れます。
新NISAは、より多くの資金を非課税で運用できる制度へと進化して効率的な資産形成が可能です。
売却して空いた枠を再度利用できる
新NISAでは、売却した分の非課税枠を翌年以降に再利用できる仕組みが導入され、投資の自由度が大きく向上しています。
旧NISAで一度投資枠を使うと、その枠は売却しても復活せずに新たに投資するには新しい枠を使う必要がありました。
しかし、新NISAでは売却した商品分の非課税枠(購入時の価格相当)が翌年以降に再利用可能になり、より柔軟な投資計画を立てられます。
非課税枠の1,800万円をすべて使い切った後に一部の商品を売却すると、その分の枠が翌年以降も再利用可能です。
非課税枠が復活すれば、一度投資した資金を回収しつつ新たな投資機会を得られます。
この仕組みにより、新NISAは長期投資だけでなくライフステージの変化に応じた柔軟な資産運用ができる制度へと進化しました。
非課税保有期間が無期限になる
新NISAでは非課税保有期間が無期限になり、焦らず自分のペースで投資ができます。
旧NISAでは、一般NISAは5年、つみたてNISAは20年と非課税期間に制限があり、期間が終了すると売却するか課税口座に移す必要がありました。
旧NISAでは「非課税期間が終わるまでに売却すべきか」「移管後の運用をどうするか」といった悩みを抱える人も多かったです。
しかし、新NISAでは非課税期間が無期限となり、投資した商品を好きなタイミングで売却できるようになりました。
非課税期間が無期限になり長期的な資産運用がしやすく、市場の状況を見ながら無理なく投資を続けられます。
新NISAは長期的に資産を増やしたい人にとって、より安心して運用できる制度へと進化しました。
「つみたて投資枠」は手間がかからず、投資タイミングの判断が不要
つみたて投資枠では自動積立によって投資の手間がかからず、タイミングを気にせず運用できるメリットがあります。
投資では「いつ買うのがベストか?」と悩みがちですが、つみたて投資枠なら設定するだけで毎月自動的に一定額を買い付けられるのでタイミングを考える必要がありません。
毎月自動的に一定額を購入する「つみたて投資」を行えば、ドルコスト平均法を活用して長期的に安定した資産形成が可能になります。
つみたて投資を活用すれば市場の変動に影響されにくくなり、安定した資産形成が可能になります。
例えば毎月1万円ずつ積み立てると価格の変動に合わせて購入額が調整されるため、自然と購入価格が安定しやすいです。
つみたて投資枠は無理なく投資を続けられ、資産を着実に増やしたい人に向いています。
「成長投資枠」では個別株やREITなど自由度の高い投資ができる
成長投資枠では幅広い投資商品に投資でき、より積極的な資産運用が可能です。
値上がり益を狙った株式投資や不動産市場に投資するREITなど、成長投資枠の活用で自分のリスク許容度に合わせた投資戦略を立てられます。
以下の比較表で、成長投資枠で投資できる金融商品の違いを確認してみましょう。
| 投資方法 | 特徴 |
|---|---|
| 個別株投資 | 成長が期待できる企業の株を購入し、値上がり益を狙う |
| ETF投資 | 世界市場や特定の業界に幅広く分散投資できる |
| REIT投資 | 不動産市場に投資し、賃料収入や値上がり益を狙う |
| 投資信託 | 運用のプロが資産を分散し、リスクを抑えながら運用する |
成長が期待できる企業の個別株に投資しながらETFで世界市場全体に分散投資をすれば、リスクを抑えながら資産を増やすことが可能です。
成長投資枠を活用すれば、つみたて投資枠よりも積極的な投資戦略を取りたい人にとってより大きなリターンを狙えます。
100円など、少額でも投資を開始できる
新NISAでは100円などの少額から投資を始められ、初心者でも気軽に運用をスタートできます。
以下の比較表で、少額から投資できる金融商品の違いを確認してみましょう。
| 投資商品 | 最小投資金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 投資信託 | 100円~ | 少額で分散投資ができる。自動積立も可能。 |
| 単元未満株 | 数百円~ | 通常の株式よりも安く購入できるが、金融機関によって最低購入額が異なる。 |
| ETF | 1口1,000円程度~ | 株式市場で取引されるため、リアルタイムで価格変動する。 |
| REIT | 1口1万円程度~ | 不動産市場に投資できるが、最低投資額が比較的高め。 |
このように投資信託なら100円から、単元未満株であれば数百円や数千円から購入できるため大きな資金がなくても投資を始められます。
少額投資でも継続すれば、将来的に大きな資産へ成長するかもしれません。
このように新NISAでは資金が少ない人でも投資を始めやすくなり、長期的な資産形成の第一歩を踏み出せます。
新NISAのデメリット
新NISAには投資可能額の拡大や非課税期間の無期限化などのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
損益通算ができず短期的な運用には向かないなど、事前に理解しておくべき重要なポイントです。
本章では、新NISAの具体的なデメリットについて解説します。
・損益通算ができない
・投資対象の選定が甘くなる
・短期的な目線での運用
・短期資金の運用には不向き
・スイッチングできない
・海外転居時の継続が難しい
・年間投資枠と非課税保有限度額の設定
・損失は税務上ないものとされる
これらの点を理解し、新NISAを適切に活用できるようにしましょう。
それぞれの項目について詳しく見ていきます。
損益通算ができない
新NISAでは、NISA口座で発生した損失を他の口座の利益と相殺できません。
以下の表で、新NISAと旧NISAの損益通算の違いを確認しましょう。
| 項目 | 旧NISA(特定口座・一般口座含む) | 新NISA |
|---|---|---|
| 損益通算 | 可能(特定口座・一般口座では損益通算ができる) | 不可(損失は税務上なかったものとされる) |
| 損失の繰越控除 | 可能(最大3年間繰り越し可能) | 不可(損失の繰越控除は認められない) |
| 税制優遇 | なし(通常の課税が適用される) | あり(利益にかかる税金がゼロ) |
この表で記載されているように、一般口座や特定口座では売却益や配当所得の損益通算や、損失の繰越控除が可能です。
しかし、新NISAでは利益が非課税のため損失も税務上「なかったもの」と扱われ、相殺や繰越控除はできません。
例えば特定口座で100万円の利益と50万円の損失が発生した場合、損益通算によって課税対象の利益は50万円になります。
しかし、NISA口座で50万円の損失があっても他の利益とは相殺されず税負担は軽減されません。
このように新NISAは非課税のメリットがある一方で、損失が出たときに税務上のメリットが得られない点に注意が必要です。
投資対象の選定が甘くなる
新NISAでは年間投資枠や非課税保有限度額が拡大により、投資対象の選定が甘くなる可能性があります。
旧NISAでは一般NISAとつみたてNISAの投資枠が限られていたため、投資家は慎重に投資商品を選ぶ必要がありました。
しかし、新NISAでは年間最大360万円、非課税枠1,800万円に拡大されて売却で枠が復活するため安易に投資を始める人が増える可能性があります。
新NISAで投資枠が拡大されたことでSNSなどで話題の商品を十分に調査せず購入し、損失を抱える人が増えるかもしれません。
新NISAでは非課税期間が無期限のため、含み損を抱えたまま「いつか回復するだろう」と長期保有して適切な損切りのタイミングを逃してしまう可能性もあります。
このように新NISAは投資の自由度が増した反面、慎重な商品選びが求められる制度です。
短期的な目線での運用
新NISAでは、短期間の売買が増える可能性があります。
旧NISAでは一度投資枠を使うと売却しても枠は戻らなかったため、売却の判断には慎重にならざるを得ませんでした。
しかし、新NISAでは売却後に投資枠が復活するため、頻繁に売買を繰り返す投資行動が増える可能性があります。
例えば株価が下がったタイミングで購入してすぐに売れば、一時的な利益を得ることも可能です。
しかし、手数料が増えるなど長期的な資産形成の目的から外れてしまう可能性があります。
また売買手数料が収益となる証券会社は、投資家に積極的な売買を促す可能性があるため注意が必要です。
一般的にNISAは長期的な資産形成を支援するための制度ですが、短期的な利益を狙う運用が増えると本来の目的から外れるリスクがあります。
短期資金の運用には不向き
新NISAは、短期間で必要なお金を増やす目的には向いていません。
投資信託や株式は市場の変動によって価格変動があるため、元本割れのリスクがあります。
新NISAで運用をするときに、日々の生活費や5~10年以内に必要になる資金を運用するには適していません。
例えばマイホーム資金を新NISAで運用すると、市場の影響で資金が不足するリスクがあるため注意が必要です。
短期間でお金を引き出す予定がある場合は、新NISAよりも定期預金や個人向け国債などの元本保証のある資産で運用する方が適しています。
スイッチングできない
新NISAでは一度購入した商品を別の商品に乗り換える「スイッチング」ができません。
iDeCo(個人型確定拠出年金)では運用商品を変更する「スイッチング」が可能ですが、新NISAではできなくなりました。
以下の表で、新NISAとiDeCoのスイッチングの違いを確認しましょう。
| 項目 | 新NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| スイッチング(投資商品の乗り換え) | 不可(乗り換えたい場合は売却して再投資が必要) | 可能(運用中でも商品変更ができる) |
| 売却後の再投資 | 可能(売却後の枠を翌年以降に再利用できる) | できない(売却後は再投資不可) |
| 非課税メリット | あり(運用益が非課税) | あり(運用益が非課税) |
| 引き出しの制限 | なし(いつでも売却・引き出し可能) | あり(原則60歳まで引き出し不可) |
新NISAで一度購入した商品を別の商品に変更したい場合は、売却して再投資する必要があります。
しかし、売却すると市場価格が影響するため損失が発生する可能性があり、単純に乗り換えられません。
新NISAではスイッチングができないため、最初に購入する投資商品を慎重に選ぶ必要があります。
特に長期投資を前提とする場合は、運用方針に合った商品を選ぶようにしましょう。
海外転居時の継続が難しい
新NISAは日本に住んでいる人のみが利用できる制度であり、海外に転居すると継続が難しくなります。
新NISAの利用対象者は「日本国内に居住し、1月1日時点で18歳以上の人」が条件です。
そのため海外転勤や留学などで日本を離れ、非居住者になると新NISA口座の運用を続けられなくなります。
海外転勤や移住を検討している場合は、新NISAの利用計画に注意しましょう。
年間投資枠と非課税保有限度額の設定
新NISAでは、年間投資枠と生涯非課税保有限度額が設定されています。
年間投資枠は最大360万円、生涯非課税保有限度額は1,800万円となっており、それ以上は非課税での運用ができません。
以下の表で、新NISAと旧NISAの年間投資枠や非課税保有限度額の違いを確認しましょう。
| 項目 | 新NISA | 旧NISA(一般NISA / つみたてNISA) |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 最大360万円 | 一般NISA:120万円 つみたてNISA:40万円 |
| 生涯非課税保有限度額 | 1,800万円 | 設定なし(年間枠のみ) |
| 売却後の枠の再利用 | 可能(売却分の枠を翌年以降再利用できる) | 不可(売却しても枠は復活しない) |
| 非課税期間 | 無期限 | 一般NISA:5年間 つみたてNISA:20年間 |
新NISAで長期的な資産形成を考える場合は、年間投資枠の使い方や非課税枠の管理を慎重に行いましょう。
例えば新NISAでは年間360万円を5年間投資すると、1,800万円の非課税枠を使い切れます。
しかし、途中で売却するとその分の投資枠が翌年以降に戻るため、状況に合わせた資産運用が可能です。
新NISAは非課税で運用できる総額が決まっているため、計画的に投資判断をしましょう。
損失は税務上ないものとされる
新NISAでは、NISA口座で発生した損失は税務上「なかったもの」とされます。
一般口座や特定口座では、損失を確定申告すれば他の利益と相殺して翌年以降に繰り越せます。
しかし、新NISAではこの仕組みが適用されないので一度発生した損失を税制上考慮されません。
例えば特定口座で50万円の利益と30万円の損失が出た場合、損益通算によって課税対象は20万円になります。
しかし、新NISAで30万円の損失が発生しても、他の口座の利益と相殺できずに税制上の優遇措置を受けられません。
新NISAで投資を行う際は、利益が非課税になるメリットを活かしつつも損失が発生した場合のリスクを考慮しながら慎重に運用する必要があります。
新NISAを始めるには
新NISAを活用するにはNISA口座の開設や金融機関の選定など、いくつかの準備が必要です。
特に金融機関によって取扱商品や手数料が異なるため、事前に比較しましょう。
本章では、新NISAを始めるための具体的な手順について解説します。
・金融機関でNISA口座を開設する必要がある
・NISA口座開設の流れ
・金融機関を選ぶポイント
・新NISA口座の特徴と選び方
これらの手順を理解し、スムーズに新NISAを始められるようにしましょう。
それぞれの項目について詳しく解説します。
金融機関でNISA口座を開設する必要がある
新NISAを利用するには、証券会社や銀行などの金融機関でNISA口座を開設する必要があります。
NISA口座は1人1口座までと決められており、複数の金融機関で同時に開設はできません。
また金融機関ごとに取扱商品や手数料、サービスが異なるため自分の投資スタイルに合う金融機関を選ぶのが重要です。
投資信託の種類が多い証券会社や、クレジットカード積立でポイントが貯まる金融機関など、それぞれの特徴を比較して選びましょう。
自分の投資スタイルに合った金融機関を選べば、より効率的に資産形成を進められます。
NISA口座開設の4ステップ
新NISAを始めるには、金融機関でNISA口座を開設する必要があります。
一般的なNISA口座の開設手順は以下のとおりです。
口座開設はオンラインで簡単に申し込める場合が多く、流れを知っておけばスムーズに進められます。
それでは、各ステップの詳細を見ていきましょう。
NISA口座を開設する際は、自分の投資スタイルに合った金融機関を選ぶのが大切です。
証券会社や銀行ごとに取扱商品や手数料が異なるため、以下のポイントを確認しておきましょう。
- すでに証券会社や銀行の口座を持っている場合は、NISA口座のみ追加申請可能
- 新規で口座を開設する場合は、NISA口座とあわせて「総合口座」の開設も必要
- 証券会社ごとに取扱商品や手数料が異なるため、事前に比較して選ぶことが重要
例えば投資信託の取扱いが豊富な証券会社を選べば、より多くの選択肢から自分に合った商品を見つけやすくなります。
またクレジットカード積立のポイント還元がある金融機関を活用すれば、投資しながらポイントを貯めることも可能です。
長期的な資産形成を考え、自分に合った金融機関を選びましょう。
NISA口座を開設するには、金融機関に必要な書類を提出する必要があります。
特にマイナンバーの確認書類や本人確認書類は必須となるため、申し込み前に確認しておきましょう。
NISA口座を開設する際に必要となる書類は以下のとおりです。
| 書類の種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 本人確認書類 | 本人の身元を確認するための書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| マイナンバー確認書類 | マイナンバーを確認するための書類 | マイナンバーカード、通知カード+本人確認書類、住民票の写しなど |
| 口座開設申込書 | NISA口座の開設を申し込むための書類 | 金融機関によってはオンライン申込なら不要 |
これらの書類を金融機関に提出する方法は、主に以下の3つの選択肢があります。
申し込み方法や利用する金融機関によって異なるため、自分に合った方法を選びましょう。
| 提出方法 | 手順 | 特徴 |
|---|---|---|
| オンライン提出 | 金融機関の専用ページにログインし、スマホで撮影した本人確認書類をアップロード | 手続きがスムーズで最短即日完了する場合もある |
| 郵送提出 | 書類をプリントアウトし、必要事項を記入して郵送 | 書類の到着・確認に時間がかかるため、1週間以上かかる場合もある |
| 店頭提出 | 銀行窓口や証券会社の店舗に直接持参し、その場で確認を受ける | その場で不備を確認できるため、手続きが確実に進む |
オンライン提出を利用すれば、申し込みから最短即日で手続きを完了できる金融機関もあります。
一方で郵送の場合は書類の到着や確認作業に時間がかかるため、1週間以上必要です。
早くNISA口座を開設したい場合は、オンラインでの申し込みが可能な金融機関を選ぶとスムーズに進められるでしょう。
NISA口座は1人1口座までしか持てないため、申し込み後に税務署で重複口座がないかの審査が必要です。
NISA口座開設の審査は、以下の手順で進められます。
- 金融機関が税務署にNISA口座開設の申請を行う
- 税務署が重複口座の有無を確認
- 問題がなければNISA口座の開設が承認される
この審査には通常1~2週間ほどかかり、年末年始や年度切り替え時期など申し込みが集中する時期には3週間以上かかる場合もあります。
審査が完了するまで投資を始められないため、早めの申し込みがおすすめです。
税務署の審査が完了すると、金融機関から「NISA口座開設完了」の通知が届きます。
NISA口座開設完了の通知は、以下の方法で受け取ることが可能です。
| 通知方法 | 説明 | 特徴 |
|---|---|---|
| メール | オンライン申込の場合、登録したメールアドレスに通知が届く | すぐに確認できるため手続きがスムーズ |
| 郵送 | 書面での通知を希望すると、自宅に書類が届く | 書類として保管できるが、到着までに時間がかかる |
| オンライン確認 | 金融機関のマイページにログインして開設状況を確認する | いつでも確認でき、書類不要で便利 |
通知を受け取ったら、NISA口座を通じた投資ができます。
一部の証券会社では開設後の入金方法や投資の始め方を解説するガイドを提供しているため、投資初心者はガイド活用するとスムーズにNISA口座を運用可能です。
金融機関を選ぶポイント
新NISAを始める際は、どの金融機関でNISA口座を開設するかが重要になります。
取扱商品や手数料、ポイント還元は金融機関ごとに違うため自分に合う金融機関を選ぶのが重要です。
以下の表に、金融機関を選ぶ際に確認すべきポイントをまとめました。
| 項目 | 確認すべきポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 取扱商品 | つみたて投資枠と成長投資枠の商品ラインナップを確認する | つみたて投資枠は金融庁指定の投資信託のみ。 成長投資枠では個別株やETFの取扱いが証券会社ごとに異なる |
| 手数料 | 日本株や米国株の売買手数料が無料か、投資信託の購入時手数料がかかるか | 楽天証券・SBI証券では新NISA口座の日本株売買手数料が無料 |
| ポイントプログラム | クレジットカード積立のポイント還元があるか、投資信託の保有残高に応じたポイント還元があるか | 楽天証券は楽天ポイント、SBI証券はVポイントが貯まる |
| 取引ツールやサービス | 取引アプリの使いやすさや、投資サポートツールの充実度、カスタマーサポートの対応 | 取引アプリの操作性、リアルタイム情報の提供、電話・チャットサポートの有無を確認 |
どの金融機関が自分の投資スタイルに合っているかを比較し、最適な口座を選びましょう。
新NISA口座の特徴と選び方
新NISAを始める際は証券会社ごとの違いを把握し、自分に合った金融機関を選ぶのが重要です。
各社の手数料や取扱商品、ポイント還元の有無などを比較してよりお得に運用できます。
以下の表で主要な証券会社の特徴を確認し、自分に適した口座を選びましょう。
| 証券会社 | 特徴 | おすすめの人 |
|---|---|---|
| マネックス証券 | ・日本株の売買手数料が無料 ・米国株・中国株の売買手数料もキャッシュバックで実質無料 ・すべての投資信託の販売手数料が無料 ・投資信託の保有でマネックスポイントやdポイントが貯まる | 少額投資からコツコツ運用したい人 |
| 楽天証券 | ・NISA口座数が業界No.1 ・日本株の売買手数料が無料 ・米国株式&海外ETFの売買手数料も無料 ・楽天カード積立で最大1%の楽天ポイント還元 | 楽天経済圏を活用している人 |
| SBI証券 | ・日本株・米国株・海外ETFの売買手数料が無料 ・つみたて投資枠の対象投資信託を幅広く取り扱い ・三井住友カードのクレカ積立でポイントが貯まる ・独自のポイントプログラムが充実 | クレカ積立のポイント還元を活用したい人 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ・au PAYカードでクレカ積立が可能 ・日本株・投資信託の取引手数料が無料 ・保有残高に応じて毎月Pontaポイントが貯まる | Pontaポイントを貯めながら投資したい人 |
証券会社ごとに強みが異なるため、ポイント還元を重視するのか取引手数料を抑えたいのか、自分の投資スタイルに合った金融機関を選びましょう。
新NISAの注意点
新NISAは投資で得た利益が非課税になる魅力的な制度ですが、注意すべき点もいくつかあります。
特に投資にはリスクが伴うため、制度の仕組みを正しく理解して適切な活用方法を考えるのが大切です。
本章では、新NISAを利用する際に押さえておきたいポイントを解説します。
・元本割れの可能性がある
・長期・分散投資を心がける
・つみたて投資枠から始めるのがおすすめ
これらの点を理解し、新NISAを賢く活用できるようにしましょう。
それぞれの項目について詳しく解説していきます。
元本割れの可能性がある
新NISAを利用する際には、投資による元本割れのリスクを理解しておきましょう。
投資信託や株式は市場の価格変動の影響を受けるため、購入時よりも価格が下がる可能性があります。
短期売買は少しの価格変動が大きな損失につながる可能性があるため、注意が必要です。
景気の悪化や企業業績の低下により株価が下落すると、投資資産の価値が大きく減少します。
一時的な値下がりで焦って売却すると損失が確定してしまうため、長期的な視点で運用するのが大切です。
新NISAは長期的な資産形成を目的とした制度のため、一時的な価格変動に左右されず計画的に運用していきましょう。
長期・分散投資を心がける
新NISAを活用する際は、リスクを抑えるために長期・分散投資を意識するのが大切です。
投資信託や株式は短期間で大きく値動きし、相場の変動によって一時的に資産が減る可能性があります。
また特定の国や業界に偏った投資をすると、予期しない出来事によって資産が大きく減るリスクがあります。
そのため異なる地域や業種に投資をして、リスクを分散しながら資産を増やすのが重要です。
新NISAを利用する際は、長期・分散投資を意識しながら安定した資産形成を目指しましょう。
つみたて投資枠から始めるのがおすすめ
新NISAを始める際は、まず「つみたて投資枠」から活用するのがおすすめです。
つみたて投資枠は金融庁が厳選した投資信託のみを対象としており、長期・積立・分散投資に適した商品が揃っています。
投資初心者が長期的な資産形成を始めるときには「つみたて投資枠」から始めるのがおすすめです。
つみたて投資では価格が高いときは少なく、安いときは多く買えるのでリスクを抑えながら資産形成を進められます。
つみたて投資枠の対象商品は長期的な資産形成を目的としたものが多いため、短期間の値動きに左右されにくいですす。
投資初心者は、つみたて投資枠でコツコツと資産を増やしながら投資に慣れていくのが良いでしょう。
新NISAで賢く資産形成を始めよう
新NISAは長期投資に適した非課税制度で、コツコツ資産を増やしたい人や積立投資でリスクを抑えながら運用したい人に向いています。
つみたて投資枠と成長投資枠を併用できるため、自分の投資スタイルに合わせた柔軟な運用が可能です。
新NISAは短期売買には向かないため、長期的に資産を増やす意識を持ちましょう。
投資初心者は、つみたて投資枠を活用して少額から投資に慣れるのがおすすめです。
新NISAを上手に活用し、計画的に資産形成を進めていきましょう。
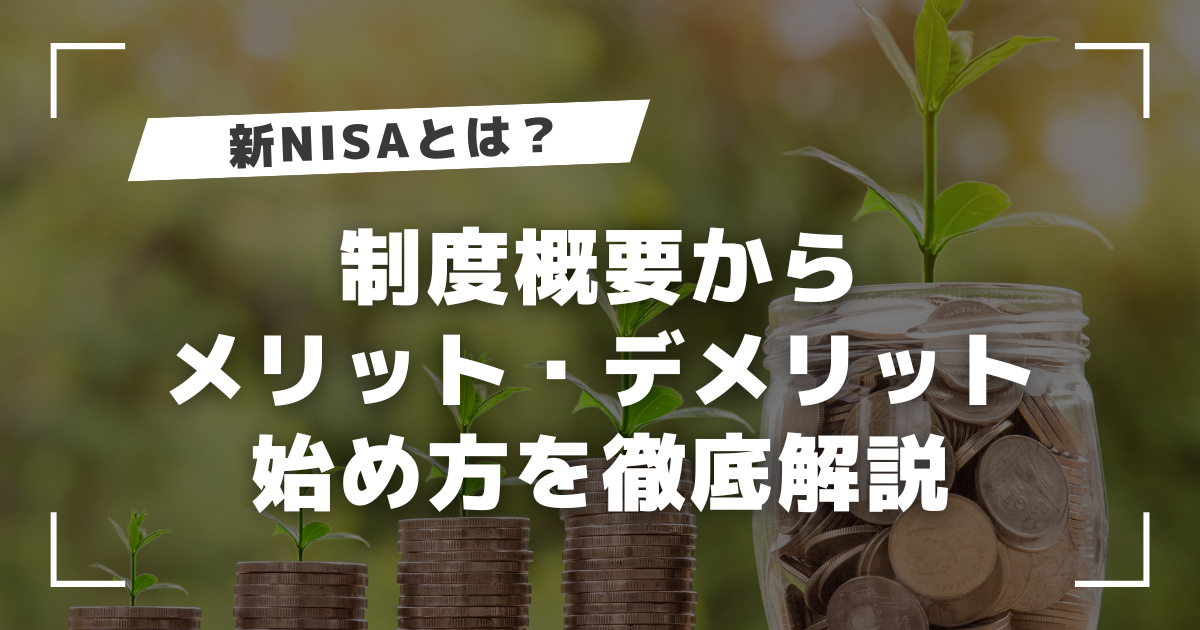
コメント